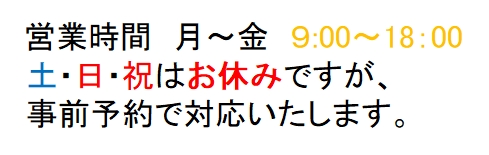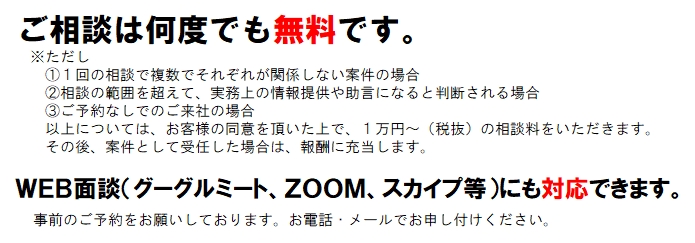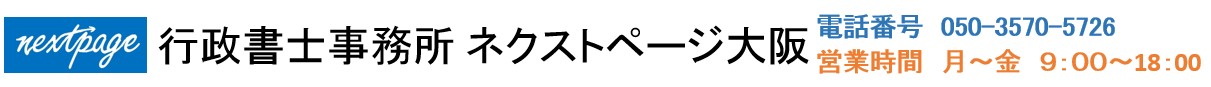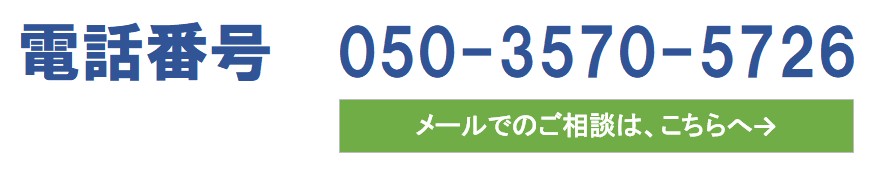後遺障害認定手続について
まず、事故に遭われたことに心からお見舞い申し上げます。
事故のショックや事故後の処理や病院通院などでお気持ちに余裕が無い中で当事務所のサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
「事故の処理は相手方の保険屋さんがやってくれるから大丈夫」とお考えが一般的ですが、後遺障害認定については「大丈夫」ではありません。
後遺障害が認められると賠償金を出す保険屋さんは、大きな出費になり利益が無くなってしまいますから、親身になってくれることはありません。
これからご説明していきますが、「ご自身で準備を進めていくこと」が後遺障害認定してもらうために大事なことになります。
当事務所では、複雑な書類作成や準備等のご支援を数多くしており、ご満足いただいております。
後遺障害認定を受けるためのポイントを、これからご案内します。
相手方保険会社との打合せ
長期間の準備等が必要でポイントを外すと申請につながらない厳しい申請になりますが、当事務所が
しっかりとご支援していきます。
事故直後から申請までの流れ
・治療について保険会社と確認
事故後、保険会社の担当者が状況確認等でご自身のもとに来られます。
この時に治療費の適用についての確認が行われます。
基本は健康保険ですが、お仕事中や通勤中の場合は労災保険が適用されますので、その適用確認を
することになります。
この時に「同意書」の作成と送付が保険会社から求められます。
同意書には、「診療情報提供について」と「医療照会について」にわけられます。
「診療情報提供」は、診断書・診療報酬明細書を取得して病院等への治療費支払のために使用され
ます。
「医療照会」は、治療状況を医師に確認して、治療費負担の打ち切り判断等を行うために使用され
ます。保険会社が直接医師に治療状況を確認できるので、
保険会社に主導権を持たれたくない場合は、この同意はしないということもできるようです。
なお「同意書」の送付が遅れますと、治療費を病院が受け取れないことになってしまいます。病院
とは長いお付き合いになるので、迷惑をかけないようにしてください。
・加入保険会社への連絡
ご自身が加入している任意保険で、搭乗者傷害保険・傷害一時金・人身傷害保険・弁護士費用特約
が使える場合がありますので、確認しておきましょう。
当事務所はじめ行政書士が代理請求した場合の報酬でも弁護士特約が使える場合がありますので、
行政書士報酬に対する「弁護士特約の適用可否」について確認しておきましょう。
・傷病名の確認、治療方針
病名・症状を確認し、治療の方針を医師との相談を行います。
後遺障害認定申請のために必要な「後遺障害診断書」を作成するのは、医師となっています。
後遺障害は「十分な治療をしたものの、将来においても回復が困難と見込まれる障害」ですので、
治療のペースや内容を詰めておくことが大事になります。
あわせて、整骨院での治療を希望する場合は先生からの了承を得てください。了承がないと自費に
なってしまうことがあります。
なお、搬送された病院が「交通事故による症状を診ない先生」であることや、ご自身の通院の関係
から転院する場合は、紹介状や説明書の作成や記載内容を詰めることになります。
通院される病院ですが、後々を考えると「神経学的検査」・「画像検査」を経て治療方針を立てら
れる先生が良いかと思われます。
特に「神経学的検査」に疎い先生の場合、後遺障害診断書の記載に困る場合があります。
この点も考えて、病院選びをするようが良いかと思われます。
・治療
負傷の状況にもよりますが、通院をしてリハビリ等の治療をしていきます。整骨院などで治療をす
る場合でも、後遺障害診断書を作成できるのは医師ですので、なるべく治療の状況を把握してもら
う上でも医師に診てもらう回数を増やしておくことが良いと思われます。
将来的に裁判で障害や賠償額について争うことになった場合は、通院歴も評価対象になりますが、
整骨院の通院歴は評価されないようです。
「先生が合わない」など理由があっても病院を変え続ける『ドクターショッピング』をされると、
後遺障害診断書を書いてもらいにくくなりますので、注意してください。
・症状固定と後遺障害診断書作成
「治療状況が一進一退で回復の兆しがない」や「保険会社からの治療費負担(だいたい120万円が
上限です)の打切通知があった」・「リハビリから6ヶ月経過したが改善しない」などのきっかけ
で症状固定=後遺障害診断書を作成することになります。
主治医に、「傷病名」・「自覚症状」・「検査結果」・「将来の見通し」等を書いてもらいます。
主張したい内容があれば、先生にお願いしてみてください。
症状が複数ある場合は、症状ごとに作成しても結構です。
当事務所では、治療時に同行して医師と診断書内容の打ち合わせに対応いたします。
後遺障害認定手続
認定手続は、「一括払い事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。
一括払い事前認定
事故相手方任意保険会社がご自身に代わって後遺障害認定手続を行い、結果を自社の賠償算定
に使用する方法です。
ご自身で資料を揃えて手続をしなくても良い分、保険会社にとって有利な点だけを集めて請求
するため(自社のご自身への支払を少なくするため)、結果に納得できるかがポイントになり
ます。
被害者請求
ご自身で資料を揃えて、相手方自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行う方法です。
資料等を自身で揃えていくのは大変なことですが、納得いくまで異議申立を含めて主張内容を
説明できる書類で請求ができます。
書類は、相手方自賠責保険会社に提出します。
当事務所では、この被害者請求に必要な書類の整理をご支援しています。
異議申立
後遺障害認定手続の結果に不服がある場合に判断の見直しを求めるものです。
見直しを求める点・具体的な理由・利用評価の誤りの指摘や新たな追加資料をだすことで、
認定結果の見直しを求めることになります。
当事務所では、この異議申立に必要な書類の整理・作成をご支援しています。
障害の種類
後遺障害は症状ごとに等級分けをしています。症状がこの等級に当たると主張することにな
ります。
症状と後遺障害認定されるポイントは、主に下記の通りです。
神経障害
ムチ打ちなどしびれが残る障害。
画像所見と神経根症状誘発テストの結果で異常所見が見られないと認定がされないようです。
醜状障害
一定以上の大きさの傷跡が残っている障害。
認定調査時に面接を受けて傷の大きさを確認されることがあります。
欠損障害
事故により切断などで体の一部を失った障害。
機能障害
関節の可動域制限が発生したもの。
変形障害
骨折の癒合がうまく行かずに偽関節や骨の変形が起こった障害。